ドイツの物理学者K.F.Braunが陰極線管(CRT Cathod Ray Tube)という表示装置(Display)の原理を発明しました。テレビに使うこの原理の表示装置は発明者の名前をとりブラウン(Braun)管と呼びます。パソコンに使うものは原理名称をとり,CRT(シーアールティー)ディスプレスと呼びました。CRTディスプレイは,蛍光面に電子銃で電子ビームを照射して発光させ画面を表示します。原理構造上,熱をもつということと厚さを薄くできないという弱点があり,高解像度の時代に対応できず役目を終えました。
 現在パソコンで使う「ディスプレイ」には,構造原理から「液晶とプラズマ」の2種類がありますが,現在は高品質の液晶ディスプレイが低価格になり,液晶ディスプレイが標準になりました。プラズマは特殊な場合で一般ユーザーが使うことはありません。
現在パソコンで使う「ディスプレイ」には,構造原理から「液晶とプラズマ」の2種類がありますが,現在は高品質の液晶ディスプレイが低価格になり,液晶ディスプレイが標準になりました。プラズマは特殊な場合で一般ユーザーが使うことはありません。
コンピュータ処理の情報(文字や画像など)を視覚的に閲覧できるようにする装置を「モニタ」または「ディスプレイ」と呼びます。日常は用途観点で「表示装置」として分類しますが,コンピュータの論理装置では「出力装置」になります。「ディスプレイ」には状態を把握する,監視するという利用目的があるため「モニター」ともいいます。
液晶ディスプレイ LCD エルシーディー Liquid Crystal Display
液晶パネルを利用した表示装置で,薄型でき消費電力も小さいという利点があります。液晶に電圧をかけるとその分子が一方方向に整列し,不透明から透明に変わるという性質があります。偏光板を置いておけば,電圧の変化で光を通すか遮断するかを制御できます。液晶自体は光を発しないため,暗い場所でも見やすいように背後から蛍光灯などで照らすバックライト方式が一般的に使われいます。
液晶ディスプレイには,単純マトリックス方式のSTNとDSTN,アクティブマトリックス方式のTTFTなどがあります。現在のパソコン用液晶ディスプレイはTFT液晶を使います。
DSTN dual scan super twisted nematic liquid crystal
STN液晶では,上から下に向かって1行ずつ順次電極から電圧をかけていきます。これに対してDSTNは,画面を上下に2分割して上下それぞれでに上から下に向かって走査し,電圧を加え,同時制御します。この方式によりコントラストと表示速度が良くなります。製造コストが安いため,携帯電話や小型の情報携帯端末で利用されています。応答速度を高め,動画表示の機能を向上させたHiアグレッシブと呼ばれるタイプもあます。
TFT ティーエフティー thin film transistor liquid crystal
1つの液晶画素を1つの半導体で制御するアクティブマトリックス方式の液晶です。画面の各ドット(画素)をICで制御します。現在のものは性能がよくなり,CRTディスプレイとほぼ同等の表示品質がえられます。以前は正面からでないと見にくいという欠点もありましたが,これも改善されました。
ディスプレイの表示方式
ディスプレイ画面の描画は,左上から水平に左から右へ,上から下へ超高速に繰り返して一画面を描画します。横への描画を「水平走査」といい,縦への描画を「垂直走査」といい,その速度を「走査周波数」で表します。垂直方向の周波数を「リフレッシュレート(refresh rate)」といい,ディスプレイの画面描画の速度を表します。この値が小さいと画面にフリッカー(ちらつき)という現象が起きます。ちらつきがある場合は70Hz以上にすると押さえられます。
マルチスキャン方式 multiscan
ディスプレイは本体から送られてくる走査信号の周波数とディスプレイ側の表示能力が一致しないと正常に表示されません。走査周波数の違いやカラー方式の違いをディスプレイ側で対応する方式です。
ディスプレイのインターフェース
現在,ディスプレイのインターフェースには3種類あります。液晶ディスプレイはデジタル信号方式ですが,変換装置を内蔵していてアナログ信号のRGB端子で使うことができるものもあります。デジタル信号のディスプレイ端子(DVI)にはデジタル専用とアナログ兼用の2種類があります。Windows7搭載機よりHDMI端子が標準となりました。

アナログRGB端子
ミニDsub15ピンという形状の端子で,本体側がメス,コード側がオスになります。従来の機種であれば必ず付いている端子でしたが,Windows7発売以後の機種ではHDMI端子が標準になりましたので,付いていない機種もあります。
デジタルディスプレイ端子(DVI Digital Visual Interface)
デジタル液晶ディスプレイを接続することを目的とした端子です。デジタル専用24ピンのDVi-Dとデジタル・アナログ兼用の29DVI-Iの2種類があります。Windows7発売以後の機種ではアナログRGB端子とHDMI端子があり,DVI端子は付いていない機種もあります。
HDMI端子(high-definition multimedia interface)
家電やAV機器向けの映像・音声入出力インタフェース規格です。パソコンと液晶ディスプレイを接続するDVIインタフェース規格を発展させたもので,パソコンと液晶ディスプレイの接続にも使います。1本のケーブルで映像と音声の入出力ができます。
現在は,ご使用機種の発売された時期のより,ディスプレイ用として装備しているインターフェースが異なります。同様のことはディスプレイ側にもいえます。単体で市販液晶ディスプレイを購入する場合は双方にどのようなタイプのディスプレイ端子を装備しているかマニュアルやカタログの仕様書で必ず確認してください。
ディスプレイのサイズ
ディスプレイのサイズは,画面対角線の長さを「インチ」であらわします。かっては,14型や19型の横縦比率が4:3で,1280×1024の解像度表示ものが主流でしたが,最近は,21.5型や24型の16:9で,1920×1080解像度まで表示可能な「フルHD」が増えてきました。映像コンテンツを見る場合はこちらが適します。
解像度
表示画面はドットで構成されています。この構成数を横×縦のドット数で表したものが「表示解像度」です。「表示画素数」ともいいます。現在の表示解像度の主な規格は以下になります。今後はテレパソ用の「フルHD(full high definition)」対応のものが多くなると思われます。
- VGA ヴイジーエー 640×480
- SVGA エスヴイジーエー 800×600
- XGA エックスジーエー 1024×768
- WXGA ダブリューエックスジーエー 1280×768
- EXGA+ ダブリューエックスジーエープラス 1440×900
- SXGA エスエックスジーエー 1280×1024
- SXGA+ エスエックスジーエー 1400×1050
- WSXGA ダブリューエスエックスジーエー 1280×854
- WSXGA+ ダブリューエスエックスジーエープラス 1680×1050
- WUXGA ダブリューユーエックスジーエー 1920×1200
当初,IBM社はPC/AT機に640×480ドット表示のVGAを採用します。その後,1024×768ドット高解像度表示のXGAを追加します。XGAを他のメーカーが使うためにはIBM社のライセンスが必要となります。このためディスプレイメーカー各社は,独自に800×600ドットや1280×1024ドットなどの拡張規格をつくります。
互換性の問題が生じ,これを解決するためにVESA(ベサ)という標準化団体が設立され,VGA拡張規格の標準化をおこないます。当初,SVGAは拡張規格全体をさしていましたが,現在は上記のような区別をします。
フルHD(full high definition)
HD映像(ハイビジョン映像)で最高画質となる走査線1080本以上の方式の通称です。解像度は1920×1080ドットになります。
ディスプレイの表示性能
ディスプレイの表示内容は,ディスプレイの表示性能のみで決まるものではありません。パソコン本体の出力解像度能力,ディスプレイの物理ドットピッチ(dot pitch),ディスプレイの表示解像度能力の3つの条件が関連してきまります。
本体の出力解像度
本体に,どのようなグラフィックボードまたはグラフィックス機能をもつチップセットを使っているかにより,サポート(出力される)されいる表示解像度や表示色数が決まります。ディスプレイ側の表示性能(表示解像度や表示色数)が低いと適切なパフォーマンスがえられなくなります。
ディスプレイの表示解像度
ディスプレイがどの程度の表示能力(解像度や色数)を持っているかです。通常は,パソコン本体の出力可能な範囲と同じかやや下回る性能のディスプレイを使用します。
ディスプレイの物理ドットピッチ(dot pitch)
物理上のディスプレイ画面は小さな蛍光体が集まってできています。物理的な画面を構成する蛍光体間の距離をドットピッチ(dot pitch)といいます。この値が小さいさくなればなるほどきめが細かくなり画質が良くなります。ドットピッチ(dot pitch)は物理上の蛍光体間の距離ですので,縮めたり・伸ばしたりすることはできません。
解像度と表示範囲
画面を構成する物理的な蛍光体はのびたり縮んだりはしませんので,同じディスプレイで表示解像度を変更すると,物理上の画面の大きさは変わらず,表示解像度のみがソフト的に変わるため下記のようになります。
- 解像度を高くすると表示する範囲が広がり,文字やアイコンなどの表示は小さくなります。
- 解像度を低くすると表示する範囲が狭くなり,文字やアイコンなどの表示は大きくなります。
大きさの異なるディスプレイ,例えば17型と22型の画面に同じ解像度で表示すると22型に表示されるアイコンや文字は17型の表示より大きくなります。
表示色数
パソコンのカラー表示には光の三原色,赤(Read)緑(Green)青(Blue)の加法混合を使います。画面上の1つのドット(蛍光体)はR(赤)B(青)G(緑)の3つの発光体で構成されています。この3つの発光体に,それぞれ256の階調をもたせることにより1677万7216色の表現ができます。これを「フルカラー(full color)」または「トゥルーカラー(True Color)」と呼びます。
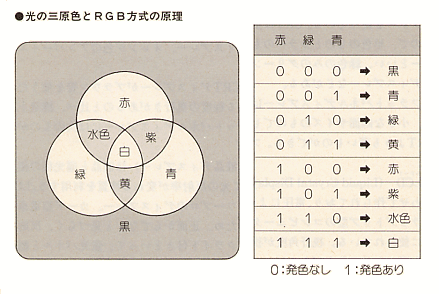
1つの基本色(1つの発光体)を256階調にするためには8ビット(28=256)の情報が必要になります。1つのドット(蛍光体)は3つの基本色(発光体)で構成されますので,1つのドットには最低24ビット(8ビット×3つ)が必要になます。表示色設定をするときに出てくる16ビット,24ビット,32ビットはこのことをさします。
通常,表示色は「16ビットカラー」「24ビットカラー」と「32ビットカラー」という呼び方をしますが,「24ビットカラー」と「32ビットカラー」の1677万7216色表示を「フルカラー(full color)」または「トゥルーカラー(True Color)」とも呼びます。また,「24ビットカラー」の1677万7216色表示を「フルカラー(full color)」と呼び,「32ビットカラー」の1677万7216色表示を「トゥルーカラー(True Color)」と呼んでいる場合もあります。
階調を上げて1677万7216色以上にしても,人間の目には判別ができないといわれます。
グラフィックスボード graphics board
グラフィックスチップやグラフィックスメモリ(VRAM)などから構成される画面表示用のボードです。グラフィックスカード,グラフィックスアクセラレーター,またはビデオボードともいいます。拡張スロットに装着して使います。以前はAGPスロット用の製品が主流でしたが,現在はPCI Express(ピーシーアイエクスプレス)規格を使います。
ディストップ型やタワー型は,解像度の対応範囲広げたり,表示速度を上げるためにグラフィックスボードを標準搭載する傾向があります。省スペース機や低価格機では表示用の機能をもつチップセットが使われ,必要なメモリはメインメモリから割り振られます。
ディスプレイで指定の表示色数をだすには,その分のグラフィックスメモリ(VRAM)が必要になります。解像度1280×1024(SXGA)で1677万7216色のフルカラーを表示するには,最低4MBのグラフィックスメモリ(VRAM)が必要となります。現在はその機種に必要な表示解像度をサポートできるグラフィックボードが標準着装されいるか,対応するチップセットを使い本体のメインメモリを利用しています。
その他ディスプレイの規格
- 輝度
- 光源となる発光体の明るさで,「CD/m2(平方カンデラ)」という単位で表します。数字が大きいほど明るくなります。
- コントラスト比
- 白と黒の明るさの比率です。比率が高いとメリハリのきいた表示になります。
- 視野角
- 左右上下から見た場合の視野角度です。「水平値/垂直値」の形式で表記されます。180度に近いほど視野角が広いことになります。
- 応答速度
- ディスプレイの表示画像を書き換えるのにかかる所要時間。用語では「速度」となっているが,単位はミリ秒を使います。一般的には「黒→白→黒」に切り替えたときの値を表記きしますが,中間色相互間の平均値表記している場合もあります。