「CPU」
CPU(シーピーユー)は「Central Processing Unit」の略で日本語では「中央処理装置」または「中央演算処理装置」といいます。処理装置という意味で「プロセッサ」と呼ぶこともあります。「CPU」はコンピューターの中枢装置です。入出力機器を制御してデータを受け取りそれに演算などの処理をして結果を出力する装置です。パソコンのCPUはその処理機能をLSI(半導体チップ)に集積してあるためマイクロプロセッサユニット ( Micor Porcessor Unit)ともいいます。略して「MPU(エムピーユウ)」と呼びます。
CPUは本体内のマザーボードと呼ばれる基盤に着装されいます。最近のパソコンCPUは周辺装置(キッシュメモリなど)などと一体化する傾向にあります。
マザーボード motherboard
パソコンの中枢となる装置や部品を配置したプリント基板のことをいいます。「メインボード 」とも呼びます。この基盤上にCPUメモリクロックジェネレータROMチップセットなどの重要な装置や部 品が取り付けられています。
下図タワー型とノート型のマザーボードです。右図はCPU部でCPUの冷却ファンを取り外 したときの状態です。
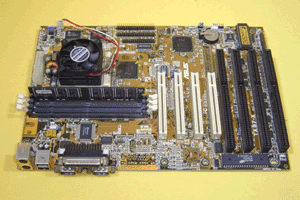
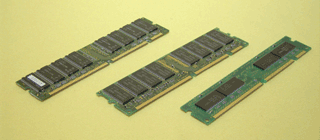
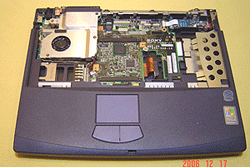

CPUは冷却装置とセットになっています。CPUの一番の敵は熱です。高温になると「熱暴 走」などと呼ばれる異常が起きます。通常使用であれば40℃から70℃ぐらいが適切とされています。
CPUの処理単位はビット
32ビットCPU64ビットCPUの区別があります。この数字が大きくなると基本的な処理単位か大きくなるため処理も速くなりますがビットは処理速度を意味する単位ではありません。現在のWindows機には32ビットCPUもありますが64ビットが主流になりました。
ビット
コンピュータは電子回路の機器です。電子回路は電気が通る/通らないまたは電圧が高い/低いという2通りの判別に適しています。このためコンピュータでは電気信号を1桁の2進数[0]と[1]に置き換えたものを基礎表現としています。「bit」は「binary digit(二進数)」を略したものです。コンピュータ基本処理の最小単位で[0]と[1]の一つの組み合わせを「1ビット」とします。詳しくは[パソコンの基本知識]-[コンピュータで使う単位の基本]をご覧ください。
動作周波数(クロック周波数)
コンピュータ内部の各装置は処理能力が異なるため同期信号で調整する必要があります。この同期信号の周波数を「動作周波数」または「クロック周波数」といいます。単位にはヘルツ(Hz)を使います。CPUではMHzやGHzを使います。カタログなどの仕様書には「CPUの型名称」と「CPUの動作周波数」が記載されています。これにより何ビット処理のどのような構造のものがどのような周波数で動作する機種であるかが分かります。
動作周波数が高くなる(数字が大きくなる)と実行される命令数が多くなり処理が早くなります。ただし動作周波数を倍にしても処理速度は倍にはなりません。パソコン内部外部の各装置にはそれぞれに動作周波数の上限がありますのでクロック周波数だけを上げても意味はありません。1MHzは1秒間に百万回1GHzは1秒間に十億回。現在は技術的にクロック周波数を上げることが限界にきており「コア」を増やすという技術に移行しています。

コア core
「コア」とはCPUの「中枢部(命令処理回路部)」のことをいいます。従来のCPUPentiumやCeleronまたは同等品は「シングルコア・プロセッサ」です。CPUの処理性能は動作周波数を上げることで改善されてきましたが発熱などの問題があり「シングルコア・プロセッサ」のCPUでは限界になりました。そこで処理性能を上げるために複数のコアを利用する技術が開発されました。「デュアルコア(dual core)」はコア部を2つにしたものです。「クアッドコア(quad-core)」はコア部を4つにして性能を向上させたものです。
Celeronは省電力・低価格が魅力のCPUですが。性能はCore iシリーズに比べるとかなり劣るため多くのアプリを同時に動かしたり複雑な作業をする用途には向いていません。 インターネット閲覧や文書作成などの簡単な作業「軽いアプリを1種類しか使わない」など単一の作業を行うパソコンに適しています。
パソコンの処理性能
パソコンの性能はパソコンを構成する各装置の性能と装置間のバランスが重要です。CPUの性能システムバスの幅キャッシュメモリの容量クロックジェネレータの周波数メインメモリの性能や搭載量使用チップセットの性能ハードディスクのアクセス速度などがあります。
各装置の仕様性能値は目安にはなりますがそのパソコの全体的な処理能力を正確に判定することはできません。このためパソコンの処理性能はベンチマークテストにより判定します。
ベンチマークテスト benchmark test
パソコンの性能評価テストのことをいいます。アプリケーションソフトの標準処理機能をそれぞれのシステムで実行しこのときの各装置や全体としての処理時間などを測定して比較します。ベンチマークテスト専用のプログラムを使っておこないます。
CPUの性能にあまり差のない場合ベンチマークテストの結果が性能値の低いCPUを使った機種の方が全体としての処理速度が速かったという報告もあります。パソコン雑誌にはときとぎ注目機種のベンチマークテスト比較が載っていることがあります。最近は「機種名」と「ベンチマーク」には見る機会の少ないデータです。
テスト用のプログラムを実行させてハードウェアやソフトウェアの性能を計測・比較することを「ベンチマークテスト」ベンチマークテストで得られた具体的な数値を「ベンチマークスコア」といいます。 ベンチマークテストによってそのハードウェアやソフトウェアの世代間の比較同世代の別製品との比較を実施できます。
CPUに使われる使用技術名称
CPUの名称に統一規格はありません。同じ意味合いの技術を使っていてもメーカーが異なると呼び方が異なります。各メーカーが独自に付けたものですのでどのような名称がどのような意味をもっているかは各メーカーのWebサイトで確認できます。名称にアルファベットや数字を付加して製造時期改良型途別性能などのタイプを表すようになっています。パソコンメーカーによりカタログの仕様書には付加記号や数字は掲載していないところもあります。逆に詳細に載せているところもあります。以下はCPUに関する技術名称で最近よく見かけるものです。CPUは日々新しい技術が開発され新しい用語がでてきます。
SSE エスエスイー(SIMD拡張命令)
Streaming SIMD Extensions
「MMX」または「SSE」はインテル社CPUのマルチメディア処理用拡張機能の名称です。当初「MMX」と呼ばれたものが改良され現在は「SSE」と呼びます。AMD社製CPUでは同等の拡張機能を「3DNow!」といいます。
現在発売されいるパソコン用CPUでは標準の機能です。CPU仕様書に「SIMD拡張命令」という項目があり「○(対応)」「×(非対応)」が付いている場合があります。ゲームや3D映像利用にはあった方がよい機能ですがビジネス用途ではなくても差し支えありません。
2次キャッシュ(L2キャッシュ)
CPUのアクセス効率を上げるために使うキャッシュメモリを指します。このキャッシュメモリの容量と周波数が大きければCPUのアクセス効率がよいことになります。
Hyper-Threading
インテル社が2001年に発表したマイクロプロセッサの高速化技術です。プロセッサ内部装置の空き時間を有効利用して1つのプロセッサをあたかも2つのプロセッサであるかのように見せかける技術です。