「レガシーインターフェース」とは「消滅または消滅危惧接続端子」のことをいいます。Windows 7の発売後,新しいインターフェース規格が次々に登場しました。従来の標準的インターフェイスの中には,その役目を終わるものがあります。
「PS/2,IEEE1284,シリアルポート」すべてUSBに置き換えられます。「SCSI(スカジー)」は技術者やマニアに根強いファンがいます。「IrDA」は無線やBluetoothになりました。
現在のマニュアルには背面図があり,どのような機器が接続できるかイラストでわかりやすく解説されています。必ず,ご使用機種のマニュアルで確認してください。一般ユーザーの方が外部増設機器を使う場合はUSB接続のものをおすすめします。
PS/2 ピーエスツー
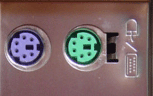 丸形状のDINという規格の端子でキーボードまたはマウスを接続する端子です。形状は同じですが,マウス用とキーボード用があり,電気信号形式が異なるため,取り違えると正常には動作しません。端子はマウス用うすい緑色,キーボード用がうすい青紫をしています。PS/2とUSBには変換コネクターがあり,マウスのコード側がPS/2端子でも,変換コネクタを使うことによりUSB端子に接続することがでます。
丸形状のDINという規格の端子でキーボードまたはマウスを接続する端子です。形状は同じですが,マウス用とキーボード用があり,電気信号形式が異なるため,取り違えると正常には動作しません。端子はマウス用うすい緑色,キーボード用がうすい青紫をしています。PS/2とUSBには変換コネクターがあり,マウスのコード側がPS/2端子でも,変換コネクタを使うことによりUSB端子に接続することがでます。
USBの普及により消滅した端子です。ノートパソコンには付いていません。
IEEE1284 アイトリプルイー1284
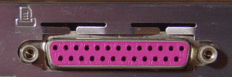 プリンターの接続などに使うパラレルインタフェース規格です。パラレルポートは通常プリンタの接続に使いますので,プリンターポートとも呼ばれます。現在のプリンターはUSB接続が主流ですが,機種により両方の端子を備えているものもあります。文字印字程度あればどちらでも処理スピードに差はありません。パラレル接続のプリンタケーブルは太く取り扱いにくいという難点があります。
プリンターの接続などに使うパラレルインタフェース規格です。パラレルポートは通常プリンタの接続に使いますので,プリンターポートとも呼ばれます。現在のプリンターはUSB接続が主流ですが,機種により両方の端子を備えているものもあります。文字印字程度あればどちらでも処理スピードに差はありません。パラレル接続のプリンタケーブルは太く取り扱いにくいという難点があります。
端子とコード
IEEE1284用のケーブル本体側はD−sub25ピン端子,プリンタ側はセントロニクス36ピン端子になります。いずれもコード側がオスで,本体と機器側がメスになります。
IEEE1284(パラレルポート)も消滅する端子です。ノートパソコンには付いていません。また,ディスクトップ機も付いていない機種が多くなってきました。
シリアルポート
 広義ではシリアルインタフェースの「ポート」を意味しますが,狭義では米電子工業会(EIA)が定めたシリアルインターフェースの「RS−232C」という規格をさします。基本ソフト(OS)上では「COMポート」と呼ばれます。シリアルポートは,アナログモデムやISDNターミナルアダプタの接続に使います。また,クロスケーブルを使いパソコン間のデータ転送にも使います。
広義ではシリアルインタフェースの「ポート」を意味しますが,狭義では米電子工業会(EIA)が定めたシリアルインターフェースの「RS−232C」という規格をさします。基本ソフト(OS)上では「COMポート」と呼ばれます。シリアルポートは,アナログモデムやISDNターミナルアダプタの接続に使います。また,クロスケーブルを使いパソコン間のデータ転送にも使います。
現在,パソコン間のデータ転送はLANを使い,アナログモデムは内蔵型のものが標準装備され,インターネットではシリアル接続のISDNターミナルアダプタは使いません。このためシリアルポートの接続端子を使うことはまずありません。
USBの普及により消滅すると思われる端子です。ノートパソコンには付いていません。
SCSI スカジー Small Computer Systems Interface
かっては,周辺機器の高速インタフェースの主流として使われましたが,拡張規格が乱立し,互換性もなく,接続端子の形状も異なる,接続設定も難しいなど取り扱いにくい点が多いため使われなくなりました。状況により趣味趣向者の方や業務用で使われていることがあります。現在はUltra SCSIやUltra Wide SCSIという規格を使います。ハードディスクや光ディスク(MO)にはこのタイプのものがあります。
SCSIは本体に接続端子がありませんのでインターフェース・ボードを使います。デイジーチェーン方式で複数台接続することができます。下写真コードの中にあるのが一番最後の機器の端子に付けるターミネーターです。

通常,一般ユーザーの方が使うことのないインターフェースです。物理的な接続端子は消滅しましたが,転送方式の技術はSATA,USB,IEEE 1394に使われています。
IEEE1394 アイトリプルイー1394
接続機器はパソコン周辺機器だけではなく,ビデオカメラやオーディオ製品など家電製品も対象。パソコンと家電機器または家電機器と家電機器を接続するときの標準インタフェースでした。ホットプラグとプラグ・アンド・プレイに対応し,転送速度最高800Mbpsの規格がありました。
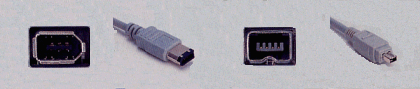
IEEE1394の名称について
アップルコンピュータとテキサス・インスツルメンツが共同で開発提案したシリアルバスの規格名称が「FireWire(ファイアワイヤ)」です。この規格を元に米国電気電子技術者協会(IEEE)が標準化したシリアルバスの規格名称が「IEEE1394」です。
ソニー社がIEEE1394と同等の規格に付けた名称が「i.LINK(アイリンク)」です。「バイオ」シリーズのカタログやマニュアルではこの名称が使われています。AV機器など家電製品に装備しているIEEE1394端子は,通常「i.LINK」と呼びます。実質的には同じものの異なる呼び方になります。
最終的に前記の著作権使用料などの問題と,USB3.0の規格がIEEE1394を上回ったためその役目を終えました。
IrDA アイアールディーエー Infrared Data Association
「赤外線データ通信協会」の略称で,同協会の策定した赤外線通信規格もさします。赤外線通信はケーブルを使いませんのでコードレスが実現できますが,遮断物に影響されやすい欠点もあります。ノートパソコンに標準搭載されていたときもありましたが,LANが普及したためため使われなくなりました。現在,コードレス製品は無線(電波)方式のものが多くなっています。キーボードやマウスなどのコードレス製品を購入したときは,説明書で赤外線方式/無線(電波)方式どちらであるかを確認し,取り扱い方をよく読んでください。
