パソコン操作に多少慣れてくると,動作環境設定に関するトラブルが増えてきます。ハードウエアの動作環境設定に関しては,設定内容の意味が分からないものは絶対に変更しないでください。ソフトウエアの動作環境設定に関しては,変更の内容と場所をマニュアルでよく確認してからおこなってください。はじめて設定を変更するものは,必ず現在値をメモしてから変更してください。
新しいソフトをインストールすると,インストール時にそのソフトウエアが自分に適した動作環境にかってに変えてしまう場合もあります。また,設定の内容の意味合いも分からないまま,裏技マニュアル本などに書いてあるとおりに設定を変更すると,それまで使っていた状態とは異なる動作環境なってしまい元に戻すことができないというトラブルがよく起きます。
メモせず分からなくなった場合は,該当ハードウエアまたはソフトウエアのサポートセンターにご相談ください。自己判断であれやこれや設定を変更しないようにしてください。Windowsに関しては「システムの復元」という機能があり,復元ポイント時点に戻すことができます。
ハードウエアとソフトウエア
ハードウエア(hardware)
コンピュータ本体を構成する各種装置やその部品。また,コンピュータに接続する各種周辺機器など物理的な機器いいます。「ソフトウエア」と対になる用語です。
ソフトウエア(software)
コンピュータで具体的な処理をおこなうためには,その処理手順をコンピュータに記録できる形式で記述した「プログラム」が必要になります。「プログラム」はいろいろな処理目的のものを作ることがで,随時修正して利用することができます。プログラムや作成データは「ハードウエア」に対して「ソフトウエア」と呼ばれます。
狭義では「ソフトウエア」と「プログラム」はほぼ同じ意味で使われますが,広義では「データ」も含めて使うこともあります。「プログラム(ソフトウェア)」は,その役割から基本ソフト(OS)とアプリケーションソフトと「その他」に大別されます。
「その他」には,アプリケーションの機能を補足いる「アドインソフト」,特殊な機能に特化した「ツールソフト」やオプションのハードウェアを制御する「デバイスドライバ」などがあります。
一体化して動作
一般ユーザーは,パソコンを物理的なハードウエア機器いうイメージで取り扱おうとしますが,実際にはハードウエアを土台として,ソフトウエアが動作している画面を見て操作しています。画面を基準に操作していますが,動作構造上は性質や役目の異なるものが連動して動作しているものを操作しています。使用者にとって,これらのものは一体化した操作性になることがよいのですが,現在のパソコンはそのような操作性にはならない部分があります。状況により,これらのものがどのような仕組みになっているかの「動作環境」の知識を必要とします。
特にトラブルが起きたときに「ハードウエア」と「ソフトウエア」の区別が必要になります。どちらにトラブルが起きているかで対処が異なります。どちらにトラブルが起きているかを取り違えますと問題を悪化させてしまう場合もあります。双方に問題がある場合はどちらか一方を解決しても解決にはなりません。
一般ユーザーがパソコンを使う場合の取り扱いにくい原因の一つに,ハードウエアとソフトウエアの「対応」という問題があります。
操作対象はひとつですが
下図は,パソコンを操作するときの対象をハードウエア,基本ソフト(OS),アプリケーションソフトに分けてイメージ化したものです。ハードを土台として基本ソフト(OS)が動作し,基本ソフト(OS)を土台としてアプリケーションソフトが動作します。
一般使用者にとって,下図の状態が理想ですが,現在は上図のような状態です。
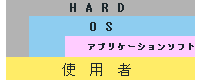

「ハードウエア」と「ソフトウエア」が一体化して,これらを意識することなくパソコンという一つの機器として利用できることが理想ですが,現在のパソコンはこれらの違いを意識して取り扱わなければならない場合があります。一般ユーザーの方が詳細な知識を身につける必要はないと思いますが,このような複数の要素から構成されるものが対応して動作していることを念頭におく必要があります。
パソコンの処理機能はハードウエアの物理的な構造のみで成り立つものではありません。パソコンの処理機能はハードウエア,基本ソフト(OS)および付随する各種の制御プログラム,アプリケーションソフトが一体となって動作することにより成り立ちます。ハードウエアだけでは正常に動作しても何ら具体的な処理はできません。ソフトウエア(プログラム)が動作することによって,はじめて具体的な処理機能をもつ機器となります。
ハードウエアの動作環境とは
パソコンは家電製品のように特定の利用目的(機能)に固定化した機器ではありません。文書を作る,計算をする,絵を描く,写真を編集する,テレビを見る,インターネットの各種サービス(メール,ブログなど)をするなど,パソコンのハードウエアとソフトウエアの組合せで実現できるものであれば何にでもで利用できます。
このため,パソコンには各利用目的に適した装置構成や処理方式があります。これを「動作環境」といいます。「動作環境」は,使用者がその利用目的に応じて設定して使えるようになっています。
現在のパソコンは性能が向上したことにより,特殊な使い方をしない限り,使用者がパソコン本体(ハードウエアレベル)の動作環境を設定をすることはなくなりました。また,パソコンの各種機能を実現するための各種オプション装置も標準装備されるようになりました。
ただし,現在もハードウエアの構造や仕組みは設定使用を前提にできています。状況により使用者が「動作環境」の設定をしなければならないこともあります。機器を増設するときや動作上のトラブルが起きたときにはこれらの知識が必要となります。
増設機器については,プラグアンドプレイという方式になり,対応している機器であれば自動的に適切な設定がされますが,接続時の手順を間違えると正しく接続されません。使用システムの利用環境によってはうまく動作しないこともあります。
増設機器メーカーのWebサイトには,使用OSごとの詳細な設定手順の説明やQ&Aコーナーがありますので必ず確認してください。
ソフトウエアの動作環境とは
基本ソフト(OS)はハードウエアに対応している必要があります。アプリケーションソフトは基本ソフト(OS)に対応している必要があります。これらを前提に機器構成や処理目的に適した動作環境設定ができるようになっています。このことが便利でもある反面,入門者や初心者にとって取り扱いにくい原因にもなります。
ソフトウエアは基本的動作環境(状態)を変更することができるようになっています。使用者のレベルや用途に適した操作性にすることができます。また,処理機能は利便性を考慮して,同じことを幾つかの方法で操作できるようになっています。指定範囲内であれば操作キーの割り振りを変更(キーカスタマイズ)することもできます。
入門者や初心者は,操作をひとつひとつ固定して覚えようとしますが,ソフトウエアそのものは動作設定を変更で,1つのことを幾通りかの方法でできるように作られています。
デフォルト default
本来の英語は「破棄,怠慢,不足,欠如」など意味する用語で,財務上は「債務不履行」の意味で使いますが,パソコンでは「規定値,初期値,標準値」という意味で使います。
あらかじめ設定されている値,または使用者が何も指示設定しないときに使われる値のことを既定値(デフォルト)といいます。ハードウエアであれば出荷時の設定状態,ソフトウエアであればインストール時の設定状態ということになります。
デフォルト値の設定変更
マニュアルやヘルプは標準設定状態を基準に説明されています。当初は標準設定で使い,慣れてきて全体の操作状態を把握できるようになったら,必要のあるものだけ変更してください。
技術的に高度な設定をしても使用者の利用環境や操作レベルに適していなければ不適切な設定になります。使用者のレベルや使用目的により適切な設定内容は異なります。
市販パソコンは,一般ユーザーが使用すると思われる目的に合わせ,ハードウエア,ソフトウエア共に適切な動作設定がされています。デフォルト値はユーザーが利用目的や好みに合わせて変更できるようになっています。